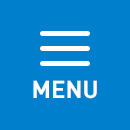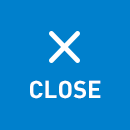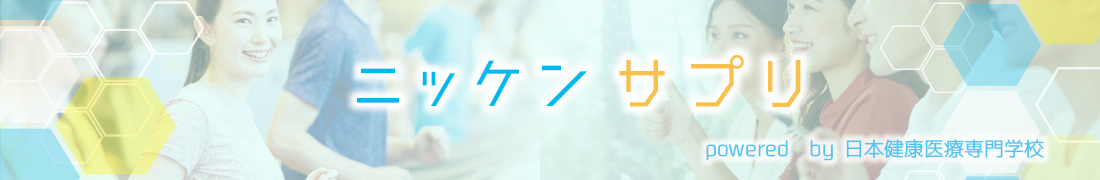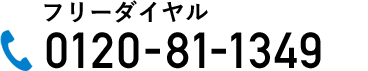鍼灸師について知る
鍼灸師として独立開業するには?開業の流れや注意点を解説
鍼灸師の資格取得後の目標として、独立開業を考える人もいるでしょう。開業を実現するためには、事前の準備が必要です。今回は、鍼灸師として独立開業をする際に何をすればよいか、開業の流れや注意点についてお伝えします。
鍼灸師になる方法や必要な資格を知りたい方は、以下もご参照ください。
―鍼灸師とは?具体的な施術内容や年収、なるために必要な資格まで徹底解説
―鍼灸師になるための資格は必要?その道のりや国家試験について
鍼灸師として独立開業するまでの流れ
鍼灸師として独立開業するには、まず国家試験に合格し、資格を取得しなければいけません。その後、鍼灸院や病院・クリニックなどに勤めて、一定の実務経験を積んだうえで開業することになるでしょう。開業する方法は、すでにある鍼灸院やクリニックなどを引き継ぐか、自分の手で新規に開業するかのどちらかです。すでにある施設を引き継ぐ場合、ある程度の開業条件は整っていることがほとんどでしょう。ここでは新規開業するケースにおいて、開業までの流れをお伝えします。
独立開業までに準備しておくこと
独立開業するためには、計画的な準備が欠かせません。まず、基本となる以下の6つのステップを順に進めましょう。
- 施術管理者の申出
鍼灸師として開業するためには、開業する地域を管轄する地方厚生局へ「施術管理者」の届出をしなくてはなりません。以前は国家資格を取得するだけで開業が可能でしたが、療養費の不正請求が問題視されたことから、新たな条件が追加されました。届出ができる要件は、1年間の実務経験と、施術管理者研修(16時間、2日間以上の講義)の受講です。届出に必要な書類等については、開業予定地を管轄する地方厚生局のWebサイトで確認してください。
参照:はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について|厚生労働省保険局長 - 開業場所の決定
施設管理者の申出をすませたら、申請した地域内で開業場所を決定します。ただし、店舗の広さや衛生面での条件があるため、どこでもよいわけではありません。鍼灸師の業務内容について規定する法律「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」により、以下の要件を満たす必要があります。
- 6.6平方メートル以上の専用施術室を有すること(柔道整復・鍼灸マッサージ師合わせて施術者が2名以上いる場合、それぞれの施術室が必要)
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
- 施術室は室面積の 7 分の1以上に相当する部分を外気に開放できること(換気扇や換気機能付きエアコンでの代替も可能)
- 施術に用いる器具、手指などの消毒設備を有すること
また、必須ではないものの、指導基準として「施術室と待合室の区画は、固定壁で仕切られていること」、「ベッドを2台以上設置する場合には、各々カーテン等で仕切り、患者のプライバシーに配慮すること」などの要件もあります。
- 鍼灸院の名称を決める
鍼灸院の名称は、病院や医師に間違えられてしまうような紛らわしい名前にしてはいけません。例えば、「科」や「医」といった表現のほか「~治療院」という名称も使用できません。加えて、流派や技術、経験などに関連する事項は使えないといったルールがあります。これらを加味して適切な名称を考えることが大切です。 - 設備の設置
鍼灸を行ううえで必要な設備を準備し、鍼灸院内に設置します。具体的には、「衛生設備」「施術台・枕・シーツ・タオルケットなどの備品」「施術室や待合室で使用する椅子・ソファー・スリッパなどの備品」「一般廃棄物と感染性廃棄物を分別するためのゴミ箱」「受付台・電話・レジ・パソコンなどの機器」「電気・水道・ガスのほか電話・ネット回線などのインフラ」「カーテンやブラインド」「書類や鍼灸に関するものを収納する設備」「セキュリティ関連の設備」「看板」などが挙げられます。 - 開設届の提出
施術管理者の申出、開業場所・名称を決めたら、開業日から10日以内に、開設者自らが開業場所を管轄する保健所に開業届を提出します。提出する書類は次のとおりです。
- 施術所開設届
- 業務に従事する施術者の資格免許証の写し※原本照合も必要なため免許所有者全員の原本も持参する
- 施術所の平面図(各室の用途・寸法および面積、ベッド・機器類の配置、施術室の外気開放部分の面積と位置または換気装置の位置)
- 建物の見取図の入った敷地の平面図(道路と敷地の位置関係がわかるもの・ビル内の場合はフロアのどこに位置するかわかるもの)
- 施術所への案内図(最寄り駅から施術所まで)
- 賃貸借契約書の写し(賃貸物件の場合)※原本照合も必要なため原本も持参する
- 定款の写し※原本照合も必要なため原本も持参する
- 保健所による施設確認
開業届を提出後、保健所の監視員が施設の確認を行います。「施術所の構造設備要件を満たしているか」「防火設備や廃棄物の管理、セキュリティ対策がなされているか」「法律にもとづいた広告が掲げられているか」などを確認し、問題なければ開業が認められます。
以上が一般的な開業の流れです。開業日をゴールとして逆算し、滞りなく準備が進められるように計画しましょう。
鍼灸院を開業する際の費用相場
店舗を借りたり建てたりする際や、設備を整えるときには高額な費用がかかります。さらに、開業後には広告を行うための予算が必要になるでしょう。事前に十分な資金を準備しておくことも大切です。
では、実際に開業するまでにはどれくらいの費用がかかるのでしょう。
一般的な新規開業にかかる費用相場は、300~600万円程度が目安とされています。ただし、立地や従業員を雇用するかどうかなどによって、必要な費用は大きく変わります。また、開業後すぐに患者が集まるとは限らず、安定した収入が得られない可能性があります。少なくとも半年先くらいまでの運転資金を用意しておいたほうがよいでしょう。開業費は、開業準備にかかる費用だけでなく、開業後のことまで考えておくのがポイントです。早い段階から具体的な資金計画を立てておきましょう。
鍼灸師として開業する際の注意点
鍼灸師としてスムーズな開業を目指すだけでなく、安定して売上を維持するためには工夫が必要です。ここでは開業に失敗しないためにやっておきたいことをお伝えします。
資金計画を立てておく
なによりも、資金がなければ開業することはできません。融資を受けることも検討しながら、開業後1~2年先までの資金計画をしっかりと立てておくとよいでしょう。融資を受ける際にも、事業計画や資金計画が明確なほうが有利です。
開業届提出の前に保健所に相談する
開業時には、保健所の施設確認をクリアしなければいけません。事前に保健所に相談すれば、開業届提出時や監視員確認時の不備を避けられます。施設の不備が工事終了後に発覚すると、開業できないだけでなく、費用負担も大きくなってしまいます。事前に相談してスムーズな開業を目指しましょう。
広告内容に注意する
開業したことを周囲に知ってもらわなければ、患者が集まることはありません。フリーペーパーや折込チラシ、Web広告などに広告掲載を検討することになるでしょう。広告については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)」により厳しく規制されています。事前に規定を確認したうえで広告を作成しましょう。なお、広告で使用可能な事項としてあはき法に記載されているは以下のとおりです。
- 業務の種類(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう)
- 治療の種類:もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼(はり)、ほねつぎ(または接骨)
- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を示す事項
- 法律にもとづく届出をした旨
- 予約にもとづく施術の実施
- 休日または夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
「肩こりが治る」「腰痛がなくなる」といった治療効果を書いたり、料金を明記したりすることはできません。
集客対策を徹底する
患者が来なければ、経営を続けられなくなってしまいます。広告だけでなく、開業準備時にSNSを利用して情報を拡散したり、ホームページを立ち上げたりするなど、インターネットの活用を含めて集客対策を検討しましょう。
出張専門の開業も視野に入れておく
施術用の物件を借りて開業するための資金を用意できない場合は、出張専門の開業も検討してみてはいかがでしょうか。その際は、開業届ではなく、「出張業務開始届」を市区町村内にある担当部署に提出します。必要な書類は以下のとおりです。
- 出張施術業務開始届書2部
- 施術者の免許証の写し2部(原本も持参)
また、届出者(出張施術業務を開始する人)の印鑑も必要です。
ただし、出張専門であっても、折りたたみ式のベッドや衛生用品などの備品を準備する必要があります。そのために資金は用意しておかなければいけません。
独立開業をスムーズに行うには事前の準備がカギ
これから資格取得を目指す学生の段階では、独立開業は先の話だと考えるかもしれません。しかし、資格取得後の実践において、開業を視野に入れた経験を積むのか、何も考えずに働くのかでは将来に大きな差が出ます。開業を前提とすれば、鍼灸院で働いている間に手技を獲得するだけでなく、経営者としての考え方を勉強することもできるでしょう。事前の準備に早すぎることはありません。将来の目的を明確にしたうえで、計画表を作成し、それに向かって一つひとつ実現することが大切です。
日本健康医療専門学校は、鍼灸師になるための資格取得を目指せる医療系専門学校です。就職後もすぐ活躍できるような授業カリキュラムや、卒業後の進路や就職についてのサポート体制も整っています。
どんな学校なのか気になったら、オープンキャンパスにご参加ください。
―学科・コースの詳細についてはこちらから
鍼灸学科